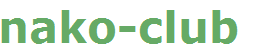奈良交通 いすゞBXD30(1966年式) 県立五條病院前-専用道霊安寺 2014年9月撮影
かつて五條から紀伊山地を貫いて新宮に至る鉄道を建設する計画があった。工事は途中まで進められ、鉄道完成までの暫定措置として、五條から城戸までバスの運行が始まった。しかし、鉄道が完成することはなく、設備の老朽化でバスの運行も取りやめとなった。
2014年秋、路線の廃止を前に、ボンネットバスが乗り入れた。写真右側の遮断機は本来の役割を果たすことなく、そこに立ち続けていた。写真右側の遮断機は役目を終えてもなお、そこに立ち続けていた。
(遮断機はバス専用道と一般道の交差点にあり、バス専用道を遮断する方向で設置されていた。(2025年3月修正))

奈良交通 日野U-RU3FSAB(1995年式)
JR奈良駅 2014年4月撮影
高架化される前のJR奈良駅舎は1934年に完成した寺院風の駅舎が象徴的であった。高架化にあたって取り壊される計画であったが、保存を望む声が強く、駅舎中央の主屋部分が曳家によって移転の上保存されることになった。現在は奈良市総合観光案内所として活用されている。
2013年から駅前広場整備工事が始まり、工事の進捗に合わせてバスのりばはたびたび移動した。写真のような位置関係でバスと旧駅舎の撮影ができたのはごく短い間のことであった。

奈良交通 日野U-HU3KLAA(1992年式) 十津川温泉 2013年11月撮影
2013年3月1日、八木新宮線が開通50周年を迎えた。これを記念して、運行車両には沿線の写真を配したラッピングが施され、記念乗車券が発売された。
高速道路を経由しない路線としては全国で最も走行距離が長いと注目を集める一方、沿線の過疎化は深刻で、県をはじめ沿線自治体で今後の路線のあり方が議論されている。

過去にほぼ同じ場所で撮影した写真。1996年3月に撮影し、1999年8月から11月まで表紙に掲載した。見比べると建屋の屋根の汚れ具合に時の流れがうかがえるが、車両は同じ形式である。
1999年8月~11月の表紙

奈良交通 日野ADG-HX6JLAE(2007年式) 平端駅 2012年5月撮影
2012年4月に運行を始めた安堵町コミュニティバス。かつては平端駅から安堵町を経て法隆寺前へ向かう路線バスが運行されていたが、久しく途絶えていた。7年ぶりに復活した路線バスが平端駅前の狭隘区間に姿を現した。

奈良交通 いすゞKC-LT233J(1998年式) 大野寺 2011年1月撮影
新春の大野寺。磨崖仏と枝垂桜で知られるこの寺は桜の頃には賑わうというが、正月の二日とあっては初詣も終わったのか、辺りはひっそりとしていた。