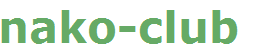「車両」に関する記事
奈良交通は2023年9月以降、順次新車を購入している。確認できている配属状況は下記のとおり。
- 観光車
- いすゞガーラ 2PG-RU1ASDJ
奈良貸切営業所(奈良200か13-04、13-05)
- 路線車
- いすゞエルガ 2RG-LV290Q4
平城営業所(奈良200か13-08、13-10、13-30、13-31、13-36、13-37、13-38)
葛城営業所(奈良200か13-09)
北大和営業所(奈良200か13-11、13-12、13-16、13-17、13-32、13-33、13-34、13-35)
奈良営業所(奈良200か13-21、13-22、13-23、13-24、13-25)
榛原営業所(奈良200か13-39)
- いすゞエルガミオ 2KG-LR290J5
西大和営業所(奈良200か13-13、13-18、13-19、13-20)
葛城営業所(奈良200か13-14、13-43)
榛原営業所(奈良200か13-15)
北大和営業所(奈良200か13-40、13-41)
観光車の導入は、2020年秋季以来3年ぶりとなる。
 榛原営業所に配属されたいすゞエルガミオ(奈良200か13-15)。今回導入の車両から行先表示は白色LEDになっている。
榛原営業所に配属されたいすゞエルガミオ(奈良200か13-15)。今回導入の車両から行先表示は白色LEDになっている。
関連記事:
特別仕様貸切バス「白虎」「玄武」を公開(2020年10月1日)
(観光車の導入は2020年度秋季の特別仕様貸切バス以来となる)
情報提供:副団長様、みえいな様、かつらぎ様、えび満月様、ながとろ様、てんらり様、エクシブ様、岸和田のあさやん様、もと様、たかばたけ様
写真撮影:829(2024年1月6日撮影、桜井駅北口)
更新履歴:2023年10月22日掲載、10月29日追記(13-09)、10月30日追記(13-11、12、14)、11月7日追記(13-13)、12月21日追記(13-16、17)、2024年1月6日追記(13-15)・写真掲載、1月14日追記(13-18~20)・写真キャプション修正、1月18日追記(13-21~25)、2月7日追記(13-30~35)、3月30日追記(13-36~43)
奈良交通は、奈良法隆寺線(奈良・西の京・斑鳩回遊ライン)にタッチ決済を導入することに合わせて、10月20日から同線をラッピングバスで運行する。
春日大社の藤の花にちなんだ薄紫色を基調としたデザインとし、他の路線と識別しやすくする。
西大和営業所所属車両のうち、8台(いすゞエルガ(LV290))にラッピングを施す。
ラッピングが施された車両の登録番号は下記のとおり。
- 奈良200か10-14、10-15、10-84、10-85、10-86、11-52、11-80、11-98
 奈良法隆寺線で運行しているラッピングバス。車両前面にはタッチ決済ができることを掲示している。
奈良法隆寺線で運行しているラッピングバス。車両前面にはタッチ決済ができることを掲示している。
情報源:奈良交通ホームページ
情報提供:もと様
写真撮影:829(2023年11月9日撮影、県庁東-県庁前)
更新履歴:2023年10月19日掲載、12月2日追記(登録番号、写真掲載)
奈良交通は2023年1月以降、順次新車を購入している。確認できている配属状況は下記のとおり。
- 路線車
- いすゞエルガ 2RG-LV290Q3
西大和営業所(奈良200か12-75、12-76、12-77、12-88、12-79)
北大和営業所(奈良200か12-80、12-81)
- いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4
奈良営業所(奈良200か12-82、12-83)
西大和営業所(奈良200か12-84)
榛原営業所(奈良200か12-85、12-86)
葛城営業所(奈良200か12-87、12-88、12-89)
平城営業所(奈良200か12-95、12-96)
- 日野レインボー 2KG-KR290J4
北大和営業所(奈良200か12-97、12-98、12-99、13-00、13-01)
- 「ぐるっとバス」向け車両
- BYD J6(EVバス)
奈良営業所(エヌシーバス委託)(奈良230あ・307、・308)
 2023年1月に導入された一般路線バス(いすゞエルガ・奈良200か12-76)
2023年1月に導入された一般路線バス(いすゞエルガ・奈良200か12-76)
情報提供:kajisawa様、たかばたけ様、えび満月様、青木貴章様、押熊線様
写真撮影:829(2023年2月12日撮影、五位堂駅)
更新履歴:2023年2月13日掲載、2月16日追記(導入の月・型式の訂正、北大和配属)、2月25日追記(EVバス)、3月3日追記(エルガミオ12-89まで)、3月17日、3月23日訂正(形式の訂正)、3月28日追記(12-95~13-01)、8月26日写真掲載
奈良交通は、運行開始を延期していたEV(電気自動車)バスを、3月21日から運行する。
奈良公園周辺で運行するぐるっとバス「奈良公園ルート」と「若草山麓ルート」で各1台運行する。ぐるっとバスの運行がない日は、郡山若草台線など他の路線で運行する。
3月21日、予定どおりEVバスの運行が始まった。
 ぐるっとバス「奈良公園ルート」向けに導入されたEVバス(BYDジャパンJ6・奈良230あ・307)
ぐるっとバス「奈良公園ルート」向けに導入されたEVバス(BYDジャパンJ6・奈良230あ・307)
 ぐるっとバス「若草山麓ルート」向けに導入されたEVバス(BYDジャパンJ6・奈良230あ・308)
ぐるっとバス「若草山麓ルート」向けに導入されたEVバス(BYDジャパンJ6・奈良230あ・308)
情報源:奈良交通ホームページ
写真撮影:829(2023年3月21日撮影、東大寺大仏殿・国立博物館付近)
更新履歴:2023年3月20日掲載、8月26日写真掲載
奈良交通は奈良県と連携して、奈良公園周辺で運行する「ぐるっとバス」にEV(電気自動車)バスを2台導入する。
EVバスは電力で走行し排出ガスがないほか、エンジンの振動や変速時の衝撃もない。
車種はBYDジャパンJ6(都市型II)で、車体の大きさは県内で現在運行している小型バスと同等である。
「奈良公園ルート」と「若草山麓ルート」で各1台運行する。ぐるっとバスの運行がない日は、郡山若草台線など他の路線で運行する。
EVバスは当初、2月25日に運行を開始する予定であったが、延期されることになった。変更後の運行開始日は未定である。
BYD製EVバスをめぐっては、部品のさびを防ぐために六価クロムが使用されていることが判明した。メーカーは通常の運行で人体への影響はないとしているが、日本自動車工業会の自主規制では六価クロムの使用が禁じられている。国内各地の事業者では、同社製車両の運行見合わせや導入延期が相次いでいる。
奈良交通は、安全性が確認できるまで、このEVバスの運行を見合わせる。一方、EVバスを導入する方針に変わりはないとしている。
情報源:奈良交通ホームページ、奈良県報道資料「県内路線における初のEVバス導入について」(2023年2月14日)、
ビーワイディージャパン株式会社サイト、一般社団法人日本自動車工業会サイト、日本経済新聞電子版「BYD日本法人、バスに六価クロム 「人や環境影響なし」」(2023年2月23日)、NHK「奈良交通 EVバス運行見合わせ “部品に有害物質”報道受け」(2023年2月24日)
更新履歴:2023年2月16日掲載、2月24日、2月25日追記